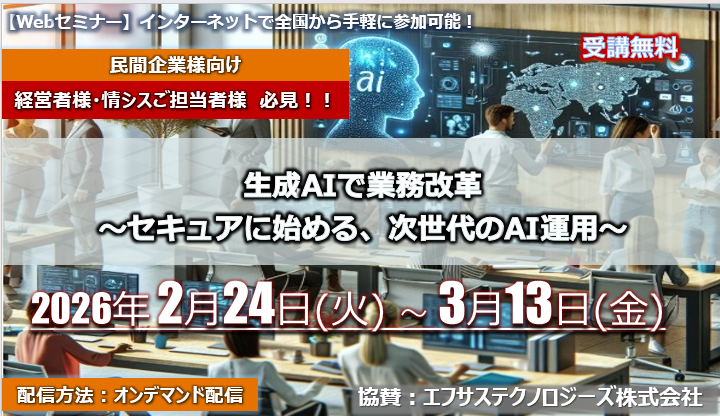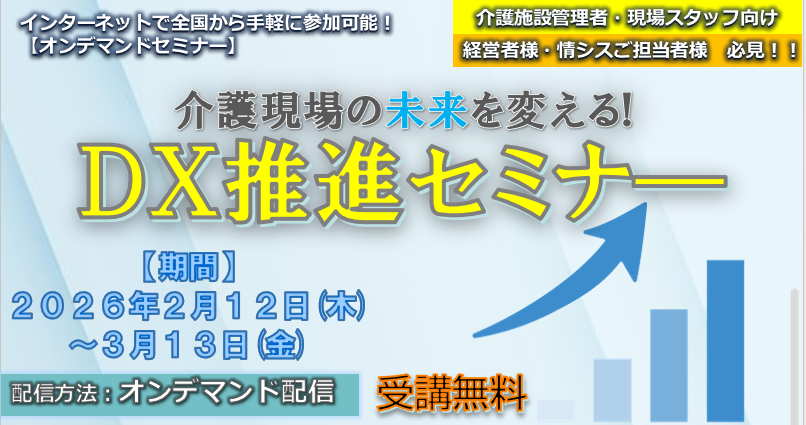【電話クレーム対応マニュアル】手順とポイント、具体的なフレーズをご紹介

企業活動において避けて通れないのが「電話でのクレーム対応」。取引先や顧客と連絡を取る際には必要なコミュニケーション手段ですが、会話のやり取りや感情の表現など、ちょっとしたやりとりが信頼関係を左右することも…。
クレーム対応に慣れていない担当者は、突然の苦情電話にどのように対応すれば良いかわからず、戸惑ってしまうことも少なくないでしょう。
最近では、多くの企業が「電話クレーム対応マニュアル」を整備しています。業種業態を問わず、人手不足が深刻化する中、業務の効率化とマニュアル化が注目されており、電話対応においても属人化を避けることが重要になってきています。
そこで、この記事では「電話クレーム対応マニュアル」の作成に役立つ基本的な手順や対応のポイント、具体的なフレーズ例までを丁寧にご紹介いたします。
電話クレーム対応の重要性
冒頭でもお伝えしましたが、ビジネスにおいて顧客が存在する以上、意見や立場の違い、直面した問題などからクレームに発展する潜在的なリスクを抱えています。
また、チャットボットでの会話対応やWebマニュアル、ウェビナーでの勉強会など顧客課題や不満を払拭する代替案は多くありますが、1対1で顧客と直接会話できる電話は顧客対応において重要なコミュニケーション手段の一つとして活用されています。
本章では、企業の電話クレーム対応の重要性について、クレーム対応が企業にもたらす影響と、電話クレーム対応のマニュアル化が必要な理由の2つの側面から確認していきましょう。
クレーム対応が企業にもたらす影響
企業に寄せられるクレームは、一見ネガティブなものに捉えられがちですが、適切に対応することで逆に顧客満足度の向上や信頼回復につながる貴重なチャンスです。特に電話によるクレームは、相手の感情や緊急性がダイレクトに伝わるため、リアルタイムでの柔軟かつ丁寧な対応が求められます。
もし対応を誤れば、クレームが長期化し、取引関係の悪化やSNS等での企業イメージの毀損を招くリスクも高まります。反対に、真摯な対応を通じて「この会社は信頼できる」と感じてもらえると、顧客のロイヤルティ向上や継続取引の確保にもつながるのです。
なぜマニュアル化が必要なのか
このように、毒にも薬にもなる電話クレーム対応ですが、電話対応のスキルや対応力は個人差が出やすく、属人化しやすい業務の一つといえます。そこで、業務の標準化・効率化が求められる昨今、誰が対応しても一定の品質が担保される「電話クレーム対応マニュアル」の整備が不可欠となっています。
業務の属人化やブラックボックス化は、組織の柔軟性や持続力を損なう要因となってしまいます。また、電話クレームは担当者の心理的な負担が大きいため、対応フローや適切なフレーズが明記されたマニュアルがあることで、安心して業務に臨めるようになり、離職リスクの軽減にも寄与します。
電話クレーム対応の基本ステップ
電話クレームの対応には、状況に応じた柔軟性と、一定の手順に基づく安定した対応力が求められます。
ここでは、担当者が迷わず落ち着いて対応できるよう、4つの基本ステップをご紹介します。
初動対応
電話対応の印象は、オペレーターの第一声で決まります。クレームの電話においても、「お電話ありがとうございます。○○(会社名)の××(名前)でございます」と、落ち着いた口調で名乗ることが大切です。
相手が不満を伝えてきた場合も遮らず、まずは話を最後まで聞く姿勢を保ちましょう。話を途中で遮ると感情を逆なでしてしまう可能性があるため、相手の言葉に相づちを打ちながら、受け止める姿勢を示すことが大切です。
内容の正確な把握と共感表現
相手の不満や要望を正確に把握するために、まずは「ご不便をおかけして申し訳ございません。詳細をお伺いしてもよろしいでしょうか」と丁寧に断った上で、事実と感情の双方に注意を払いながら顧客の話に耳を傾けます。
事実確認をおろそかにすると社内で適切な対応が行えないばかりか、相手に不信感を与える事にもつながります。同時に「お気持ちはよくわかります」「ご不快なお気持ちにさせてしまい申し訳ありません」といった共感の言葉を添えることで、相手の感情を和らげる効果が期待できます。
社内共有と対応方針の確認
内容を把握できたら、迅速に社内関係者と情報共有を行います。特に、納品ミスや契約条件の相違など、重大な内容の場合は、共有のスピードがクレーム処理の質を左右します。
ここで活用したいのが「CallKeeperDX」のような通話録音・管理ツールです。録音した音声をもとに正確な伝達が可能となり、情報の食い違いや認識ミスを防止できます。複数の関係者がリアルタイムで録音データを共有・確認できる仕組みは、社内の迅速な意思決定を後押しします。
迅速な対応とフォローアップ
クレームへの対応はスピードが命です。社内確認の上で、可能な範囲で即日中に一次回答を行うのが理想です。たとえ結論が出せなくとも、「本日中に状況のご報告をいたします」といった途中報告を忘れないようにしましょう。
問題解決後は「本日は貴重なご指摘をいただきありがとうございました」と丁寧に感謝を伝えることも忘れずに。感謝とフォローの一言で、信頼の再構築につながります。
実践に使える!電話対応フレーズ集
電話クレーム対応においては、内容だけでなく「どう伝えるか」が極めて重要です。声のトーンはもちろん、言葉選びによって相手の印象を大きく左右するためです。ここで、場面ごとにすぐ使えるフレーズをまとめてご紹介します。
クレームを受けたときの第一声
丁寧さと落ち着きを意識したフレーズを用いましょう。
「お電話ありがとうございます。〇〇株式会社の△△でございます。」
「ご迷惑をおかけしております。まずはお話を詳しく伺わせていただけますか?」
といったフレーズが有効です。
謝罪と共感を伝える言い回し
相手の気持ちに寄り添う姿勢を示すことで、落ち着かせることができます。
「このたびはご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。」
「ご指摘の通りでございます。ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
「そのような状況に置かれたことを、深くお察しいたします。」
のようなフレーズが有効です。
感情面への共感が伝わる表現を意識すると効果的です。
案内・対応方針を伝えるときの表現
状況の確認や対応方法を説明する際は、冷静かつ明確に伝えましょう。
「ただいま確認を進めております。詳細がわかり次第、改めてご連絡させていただきます。」
「関係部署と協議の上、至急、対応を進めてまいります。」
「○日までにご報告できるよう努めております。」
といったフレーズを使いましょう。
クレーム終息時のフォローアップの言葉
クレーム対応が終わった後こそ、信頼関係を回復するチャンスです。
「このたびは貴重なご指摘をいただき、誠にありがとうございました。」
「今後はこのようなことがないよう、社内で再発防止に努めてまいります。」
「ご不便をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。」
といったフレーズが有効です。
フォローアップを通じて丁寧な印象を残すことで、顧客満足度向上につながります。
クレーム対応力を高めるためのポイント
電話クレーム対応に関するマニュアル整備は重要ですが、クレーム対応は、単なるマニュアル通りの処理だけでは十分とはいえません。現場対応力を高めるには、日常的なトレーニングと知識の共有体制が不可欠です。
そこでここでは、組織としてクレーム対応力を強化するための具体的な取り組みを紹介します。
研修とロールプレイの実施
まず重要なのは、実践に近いかたちでの「ロールプレイ(模擬対応)」を含む研修の定期的な実施です。
マニュアルを読んだだけでは、実際のクレーム対応時にどう動けば良いかを即座に判断するのは難しいものです。ロールプレイを通じて、声のトーンや言葉遣い、相手の感情にどう寄り添うかといった「感覚」を身につけることができます。
研修では実際のクレーム事例をもとにしたシナリオを使用し、参加者全員で振り返りを行うことで、対応の良し悪しや改善点も明確になります。
ナレッジ共有とマニュアルの改善
次に、クレーム対応に関する知見や成功例、注意点などを全社的に共有する体制づくりが大切です。これは属人化の排除にもつながります。
たとえば、「対応ログ」や「よくある問い合わせ事例」「言い回しテンプレート」などを蓄積し、誰でもアクセスできる形で管理しておくとよいでしょう。
ここで「CallKeeperDX」のような通話録音・管理ツールを活用すれば、実際の会話データを教材として活用することもできます。録音内容から優れた対応例を抜粋し、マニュアルや研修資料に反映すれば、よりリアルで実践的なナレッジの蓄積が可能となります。
また、マニュアルは一度作って終わりではなく、現場のフィードバックやクレーム傾向の変化に応じて、定期的に見直すことが求められます。PDCAを回す仕組みを取り入れ、常に「現場で使えるマニュアル」であるよう更新を続けましょう。
まとめ
電話でのクレーム対応は、企業の信頼性を左右する重要な顧客接点となります。属人化を防ぎ、誰もが一定水準の対応を行える体制を整えることが、組織のクレーム対応力を底上げします。そのためには、日々の対応を記録・分析できる仕組みの導入も不可欠です。
たとえば「CallKeeperDX」のような通話録音・管理ツールを活用すれば、実際の対応内容をもとにしたマニュアル整備や研修設計も可能となり、より実効性の高い体制構築が期待できます。
今後のクレーム対応を、単なるトラブル処理ではなく「信頼を深めるチャンス」として活かすために、ぜひ貴社でも対応体制の見直しとマニュアル整備を進めてみてはいかがでしょうか。
CallKeeperDXのサービスページはこちら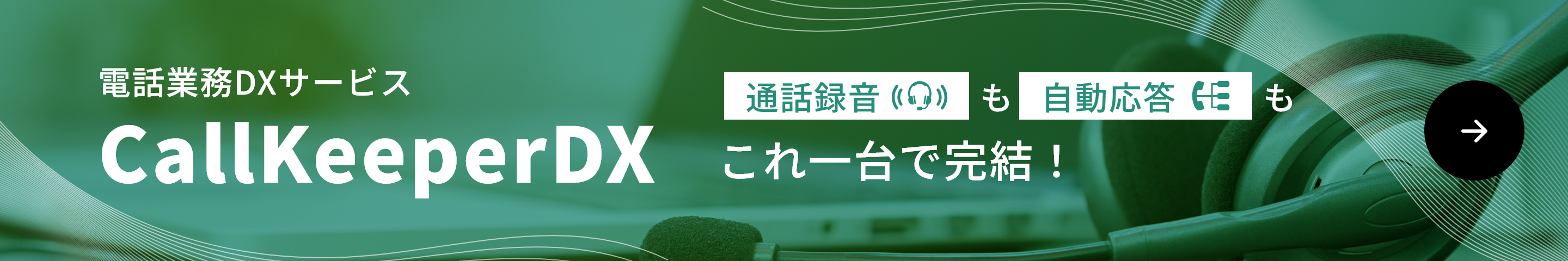
著者情報

辻 周平
扶桑電通株式会社 ビジネス推進本部
企画部 パッケージ推進課 チーフ
1982年生まれ 香川県出身。2010年扶桑電通株式会社入社。同社関西支店にて運送、製造業界を担当する営業としてお客様の業務課題の解決に向けたICTの導入を数多く経験。
その後2020年に現在のマーケティング職に異動し、お客様の電話を使った業務やカスタマーサポートのプロセスの最適化や効率化、利便性向上等電話業務全般に関わるコンサルティングに従事。日々お客様の電話業務にまつわる課題解決に取組んでいる。