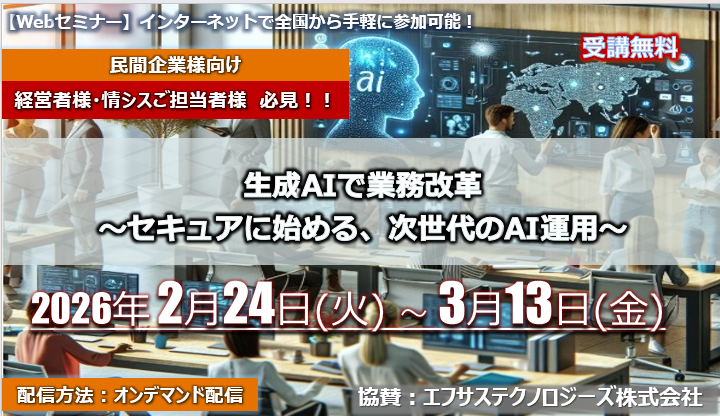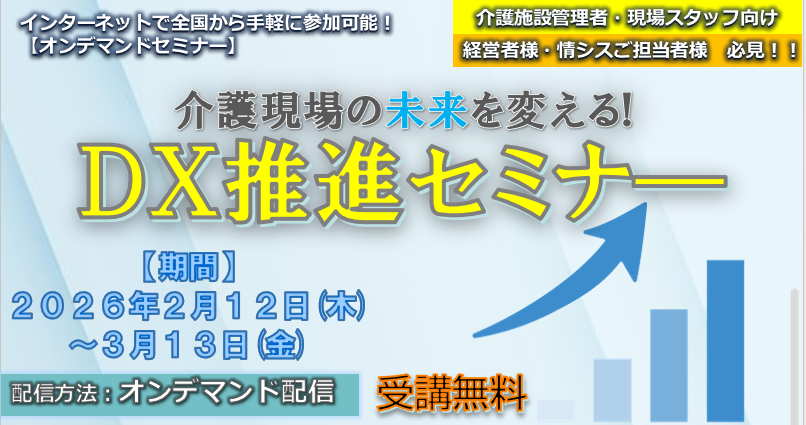電子カルテを導入するメリットと選ぶ際のポイント

医療分野では、業務効率化や医療サービスの向上のため、IT化に取り組んでいます。その一つが、紙のカルテ(診療記録)を電子化し、一元管理できるようにした電子カルテです。本記事では、電子カルテの役割や普及状況、導入するメリット、システムを選ぶときのポイントを分かりやすく解説します。
扶桑電通が誇るヘルスケアソリューションの概要資料はこちら!
電子カルテとは
そもそも電子カルテとは、これまで紙で管理していたカルテを電子データ化し、パソコンやモバイル端末で作成・編集・管理・記録できるようにしたシステムを指します。患者の主訴、診断、処方薬、経過、既往歴などの記載項目は、全てデータベース上で管理することが可能です。
|
紙のカルテ |
患者の主訴、診断、処方薬、経過、既往歴などの情報を紙に記載したもの |
|
電子カルテ |
カルテを電子化し、各項目をデータベースで管理できるようにしたもの |
医療機関によっては、「紙のカルテの方が書きやすい」「システムの操作に慣れるまでが大変」といった理由から、紙のカルテを使い続けるケースもあります。しかし、電子カルテシステムの普及状況をみると、紙のカルテから電子カルテに切り替える医療機関は年々増えつつあります。
電子カルテの普及状況
厚生労働省の統計によると、令和2年の電子カルテシステムの導入率は、一般病院で57.2%、一般診療所で49.9%です。[注1]つまり、全体の半数近くの病院が電子カルテを導入しています。また、平成20年のデータと比較すると、一般病院、一般診療所ともに電子カルテを導入する病院が年々広がっていることが分かります。
|
|
一般病院
|
病床規模別
|
一般診療所
|
||
|
400床以上 |
200~399床 |
200床未満 |
|||
|
平成20年 |
14.2% |
38.8% |
22.7% |
8.9% |
14.7% |
|
平成23年 |
21.9% |
57.3% |
33.4% |
14.4% |
21.2% |
|
平成26年 |
34.2% |
77.5% |
50.9% |
24.4% |
35.0% |
|
平成29年 |
46.7% |
85.4% |
64.9% |
37.0% |
41.6% |
|
令和2年 |
57.2% |
91.2% |
74.8% |
48.8% |
49.9% |
特に病床規模が400床以上の大病院では、電子カルテの導入率が91.2%です。医療現場において、電子カルテはなくてはならない存在になりつつあります。
[注1]厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf
電子カルテを導入するメリット
なぜ半数近くの病院で電子カルテが活用されているのでしょうか。電子カルテを導入するメリットは、以下のように4つあります。
- 業務効率化につながる
- カルテの記入ミスを減らせる
- 情報管理がしやすくなる
- カルテを保管するスペースが必要なくなる
業務効率化につながる
紙のカルテを利用する場合、診療情報を手書きで記載したり、別の書類に手作業で転記したりする必要があります。そのため、紙のカルテにはこれまで以下のような課題がありました。
- カルテの記入に時間がかかる
- 診療予約や受付に時間がかかり、患者を待たせる
- 紹介状や診療情報提供書などの作成に手間がかかる
電子カルテを導入すれば、医師は必要な情報を手書きではなく、キーボードで入力できます。テンプレートなども活用できるため、カルテの記入作業を大幅に効率化することが可能です。診療予約や受付の時間が短縮されるため、患者の待ち時間も少なくなります。
また、電子カルテシステムによっては、電子カルテの情報を自動で転記し、紹介状や診療情報提供書を作成する機能が利用可能です。このように電子カルテを導入すれば、紙のカルテ特有の課題を解決できます。
カルテの記入ミスを減らせる
紙のカルテの場合、記入する医師によっては文字が汚く、記載内容が判読できないケースがあります。電子カルテは判読性が高いため、ミスせずに入力することが可能です。紙のカルテの読み間違いを減らし、医療ミスを未然に防ぐことができます。
情報管理がしやすくなる
これまで、院内の情報伝達は紙のメモを用いたり、口頭で伝えたりすることが一般的でした。電子カルテを導入すれば、患者の診療情報を院内の端末からいつでもどこでも確認できます。受付の事務員や看護師のカルテの受け渡しも必要なくなるため、医療情報をスムーズに管理することが可能です。
カルテを保管するスペースが必要なくなる
国の規則により、カルテの保存期間は5年間と定められています。紙のカルテの場合、専用の保管スペースが必要です。病床規模によっては、保存すべきカルテの枚数が多く、保管スペースを圧迫するケースもあります。カルテをペーパーレス化し電子カルテに切り替えれば、物理的な保管スペースは必要ありません。特にクラウド型の電子カルテの場合は、データを保管するためのサーバーも必要ないため、保管スペースを大幅に圧縮することが可能です。
電子カルテを選ぶ際のポイント
電子カルテを選ぶ際、どのような点に気をつければよいのでしょうか。電子カルテ選びで失敗しないためのポイントを3つ紹介します。
使いやすいシステムか
初めて電子カルテシステムを導入する場合は、なるべく使いやすいものを選びましょう。医師や看護師、事務員にパソコンの操作が不慣れな人がいる場合、「電子カルテを導入したが、紙のカルテの方が便利だった」「操作が難しく、紙のカルテよりも入力に時間がかかる」といった事態が起きかねません。可能であれば、無料トライアルを利用し、電子カルテシステムの操作感を確かめましょう。
また、レセプトシステムやオーダリングシステムなど、他の医療システムとスムーズに連携ができる製品を選ぶことも大切です。
サポート体制は充実しているか
サポート体制が充実した電子カルテを選ぶことも大切です。例えば、システムによっては専任の担当者が病院を訪問し、電子カルテの使い方を説明してくれるケースもあります。電子カルテの操作方法で分からないことがある場合も、すぐに問い合わせることが可能です。
電子保存の3つの基準を満たすシステムか
厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」において、電子カルテを保存する際の3つの基準を示しています。[注2]
|
真正性の確保 |
電子記録の改ざんや書き換え、消去、虚偽の入力を防ぐための仕組みがあること |
|
見読性の確保 |
患者の要求に応じて、肉眼ではっきり視認できる状態で電子カルテを提示できること |
|
保存性の確保 |
法令で定められた期間(電子カルテの場合は5年間)にわたって、真正性・見読性の2つの基準を満たした状態で電子カルテを保存できること |
電子カルテシステムを導入する場合は、真正性・見読性・保存性の3つの基準を満たした製品を選ぶことが大切です。
[注2]厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」P56
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/000936160.pdf
【まとめ】
操作性の高い電子カルテを導入して業務効率化につなげよう
医療機関では、紙のカルテを電子カルテに切り替え、電子データで管理するケースが増えてきました。令和2年の統計では、一般病院の57.2%、一般診療所の49.9%で電子カルテが活用されています。[注1]
電子カルテを導入すれば、受付業務の効率化や入力ミスの減少といったメリットの他、診療情報をリアルタイムに管理できます。電子カルテシステムを選ぶ場合は、厚生労働省のガイドラインを満たす製品かどうか確認しましょう。電子カルテの導入が初めての場合は、操作しやすいシステムやサポート体制が充実したシステムを選ぶと安心です。
[注1]厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000938782.pdf
[MOU1]保管スペースの削減