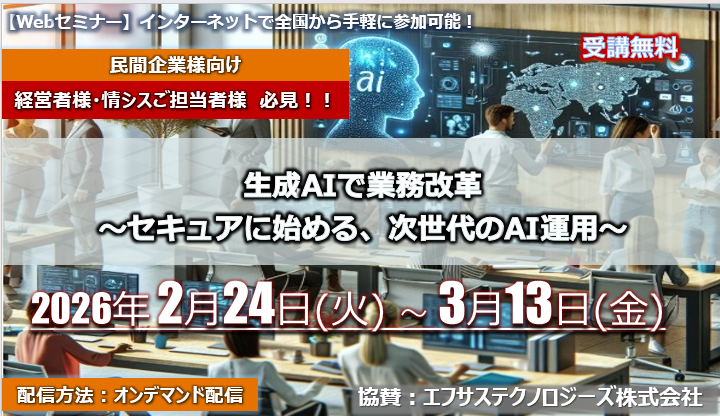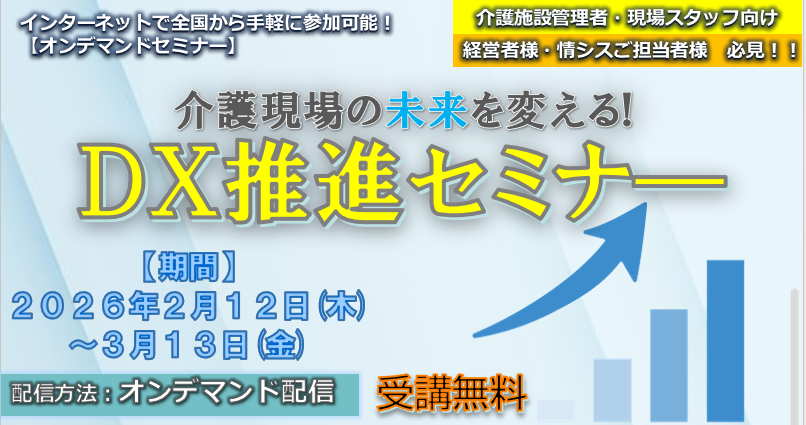IVR(電話自動応答システム)とは?メリットや活用例を解説!

IVR(電話自動応答システム)とは、電話着信時に自動でメッセージを流し、お客様に番号をプッシュしてもらう事で目的の部署に電話を転送したり次のメッセージに進んだりと、次に行う動作を変更する事ができるシステムのことです。
業務効率化や顧客対応の質向上を実現するための重要なツールとして、多くの企業で活用されており、特に営業時間外の対応や顧客からの問い合わせを迅速に処理する機能が注目されています。
日本では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進などに伴い、IVRの導入が増加しており、業種を問わず幅広い分野での活用が進んでいます。
本記事では、IVRの基本的な仕組みやメリット、さらに具体的な活用例について詳しく解説します。
- IVR(電話自動応答システム)とは?
- IVR(電話自動応答システム)の仕組み
- IVR(電話自動応答システム)の種類
- IVR(電話自動応答システム)を導入するメリット
- IVR(電話自動応答システム)のデメリット
- IVR(電話自動応答システム)の活用例
- IVR(電話自動応答システム)の選び方
- まとめ
IVR(電話自動応答システム)とは?
IVR(電話自動応答システム)とは、電話着信時に自動でメッセージを流したり、お客様に番号をプッシュしてもらう事で次に行う動作を変更したりするシステムのことです。
なお、IVRはInteractive Voice Responseの頭文字を取ったものです。
顧客が電話をかけた際に、まずガイダンスが流れます。このガイダンスに沿って顧客がプッシュボタンを押すと、選択した内容に沿った音声が流れ、顧客はその指示に従うことで目的の情報を得たり、担当部署に誘導してもらったりすることができます。
IVR(電話自動応答システム)は24時間稼働できるため、営業時間外でも顧客の問い合わせに対して情報を提供したり、必要な処理を受け付けたりすることが可能です。
IVR(電話自動応答システム)の仕組み
では、IVR(電話自動応答システム)は、どのような仕組みになっているのでしょうか?
IVRはどのように機能するのか
IVR(電話自動応答システム)は、着信時に音声ガイダンスを再生し、発信者に対して番号入力(プッシュ操作)や音声入力を促すことで、次の処理を自動的に決定・実行するという仕組みになっています。
この仕組みを活用することで、たとえば「商品についてのお問い合わせは1を、請求関連は2を…」という案内に応じて、適切な部署や担当者、または自動応答へとつながるフローを構築できます。
あらかじめ設定されたシナリオやフローチャートに従って操作を促せるため、ヒューマンエラーの防止や対応品質の均一化などにつながります。
IVR(電話自動応答システム)の種類
IVR(電話自動応答システム)は、その仕組みや活用方法に応じていくつかのタイプに分類できます。
どのタイプを選ぶかは、企業の業務内容や顧客対応方針、既存のシステムとの連携状況によって変わってきます。
以下に主要なIVRの種類をご紹介します。
ツリー型(階層式)IVR
最も一般的な形式で、「1番を押すと商品案内」「2番を押すとサポート」といったように、複数の選択肢を階層的に案内していく仕組みのIVRです。
比較的、安価に導入でき、応対内容が明確な業種に適しています。
このため、中小企業やコールセンターの一次受付などでよく使われています。
音声認識型IVR
顧客がプッシュ操作を行うのではなく、自然な音声で話しかけるとシステムが内容を解析し、次の処理を判断するタイプのIVRです。
より直感的で柔軟な対応が可能なため、サービス業などに向いています。
AIとの連携で精度向上が進んでおり、ハイエンドな顧客体験を提供したい企業で導入が進んでいます。
クラウド型IVR
オンプレミス(自社設置型)と異なり、インターネットを通じて利用するIVRです。
初期費用が抑えられるほか、遠隔地からの設定変更や利用状況の可視化も可能です。
ハイブリッド型IVR
ツリー型と音声認識型を組み合わせたシステムです。
発信者の状況に応じて操作方法を自動的に切り替えることで、ユーザー体験の最適化とシステム負荷の分散を実現します。
多様な顧客層を持つ企業や、B2B・B2C両方の窓口を持つ業種に適しています。
IVR(電話自動応答システム)を導入するメリット
IVR(電話自動応答システム)を導入することで、主に次の5つのメリットが得られます。
電話取次業務の負担を軽減できる
IVR(電話自動応答システム)を導入すれば、一次対応はガイダンスで行え、担当部署への振り分けも自動で行ってくれます。
このため、電話取次業務の負担を軽減できます。
受電や取次はシステムに任せて自動化し、人は人にしかできないもっと高度な電話応対に専念できます。
顧客満足度を向上できる
顧客からの受電に人が対応する場合、電話に出た人のスキルや、その時の忙しさなどによって対応の品質が変化してしまいます。
IVR(電話自動応答システム)なら、あらかじめ録音した内容と設定した振り分けによって、均一かつ高品質な電話対応が行えるため、顧客満足度の向上につながります。
機会損失を防止できる
顧客からの電話に人が対応する場合、電話が集中してしまうと、つながらなかったり待たせられたりします。その結果、途中で問い合わせをやめてしまう顧客も出てきます。これがひいては、受注の減少や顧客ロイヤルティの低下などにつながってしまいます。
IVR(電話自動応答システム)を活用すれば、すべての受電に対してシステムがスピーディに対応できるため、顧客の意欲を低下させずに済み、機会損失を防止できます。
営業時間外でもアナウンスで対応できる
人が対応する場合、営業時間外の電話は留守番電話に切り替わってしまうことになり、顧客満足度の低下や機会損失につながってしまいます。
IVR(電話自動応答システム)の場合は、システムなので、24時間365日、いつでも対応することが可能です。
問い合わせ内容に応じた適切な案内ができる
人が対応する場合、経験不足やミスなどから、適切な部署に受電を振り分けられないケースも生じます。
一方、IVR(電話自動応答システム)であれば、プッシュボタンの指示によってあらかじめ設定した情報や部門へ間違いなく自動で振り分けられるため、適切な案内が可能です。
IVR(電話自動応答システム)のデメリット
一方、IVR(電話自動応答システム)にもデメリットが存在します。
主に次の3点です。
すべての顧客にとって使いやすいわけではない
まず代表的なデメリットは、「選択肢が多すぎて迷いやすい」「必要な部署にたどり着くまでに時間がかかる」といった、操作の煩雑さです。
たとえば、高齢者やITツールの扱いに苦手意識がある顧客にとっては、ストレスになることがあります。
また、誤操作による対応の遅延や、「オペレーターに直接つながらない」という不満が蓄積されると、企業イメージにマイナスの影響を与える恐れも否定できません。
柔軟な対応が困難なケースがある
IVRは基本的に事前に設定されたシナリオに従って動作するため、イレギュラーな問い合わせや複雑な問題に即応する柔軟性には限界があります。
たとえば、仕入先からの緊急連絡や、発注トラブルのように迅速な人の判断が求められる場面では、IVRの対応が遅れやすくなることがあります。
このような場合に備え、一定条件を満たした場合のみオペレーターへ自動転送する仕組みを取り入れるなど、バランスを取った設計が求められます。
初期設定と運用設計に専門知識が必要
もう一つの課題は、IVRの初期設定やメンテナンスに一定の専門知識が必要な点です。
電話システムやCTIとの連携、シナリオ設計に精通した人材が求められます。
しかし、近年は直感的なUIで設定ができ、クラウド上でメニュー編集やフロー管理が可能なツールも登場しています。
こうした製品を活用すれば、運用負荷を抑えつつ、必要に応じて柔軟な変更が可能です。
IVR(電話自動応答システム)の活用例
IVR(電話自動応答システム)の具体的な活用例を4つ、ご紹介いたします。
受電の一次対応(自動受付)
IVR(電話自動応答システム)を活用すれば、顧客からの受電の一次対応を任せられます。
自動で受け付け、受電時に人が対応する必要がなくなります。
顧客が選択肢をプッシュボタンや音声で選ぶと、適切な部署や情報に案内されるため、顧客の待ち時間が短縮され、問い合わせの処理がスムーズになります。
営業・迷惑電話の振り分け(受電制御)
仮に、営業やいたずらを目的として電話をかけたとしても、IVR(電話自動応答システム)でアナウンスされた選択肢の中にはマッチする振り分け先がないため、そこであきらめて電話を切ると考えられます。
それでもしつこくかかってくる営業・迷惑電話があれば、電話番号をブラックリストとして登録すれば、適切にフィルタリングする機能を備えています。
よくある質問への自動対応
頻繫に問い合わせのある質問について、IVR(電話自動応答システム)を活用して、自動音声で回答を行うという活用方法です。
これにより、業務効率化と顧客満足度の向上を図ることができます。
他システムとの連携
IVR(電話自動応答システム)を安否確認システムやSMSなど、他システムと連携することで、音声のやりとりだけでは難しい手続きを実現できます。
たとえば、従業員の安否確認や、決済手続き用のURLの案内、本人確認などが行えます。
IVR(電話自動応答システム)の選び方
IVRシステムの選定では、自社の業務内容や顧客対応の目的に合った機能が備わっているかを見極めることが重要です。
価格や導入のしやすさだけに注目するのではなく、「どのような課題を解決したいのか」「誰が運用・管理するのか」といった視点から総合的に判断しましょう。
以下で、特に注意すべきポイントをご紹介します。
操作性と設定の自由度
IVRを導入する際に最初に確認すべきは、社内の誰でも簡単に操作・設定できるかどうかです。
特に中小企業や専任のIT担当者がいない企業では、専門知識がなくてもガイダンスの変更やフローの追加ができる操作性が重要です。
顧客対応のスムーズさ
IVRの目的は、顧客をスムーズに必要な対応先へと導くことです。
階層が深すぎたり、選択肢がわかりにくかったりすると、かえって顧客のストレスを増大させる可能性があります。
したがって、選び方のポイントとしては「最短ステップで目的の部署にたどり着ける導線が設計可能か」という観点が欠かせません。
対応可能な回線や連携機能
IVRはCTIシステムの機能の一つですが、顧客情報の一元管理とスムーズな別ツール間での情報の受け渡しによる利便性の向上もツール選定する際には意識するポイントになります。
顧客情報は利用する部署でCRM、SFA、CTIなどシステムが異なりますので、API連携や外部DB連携の可否など既存の利用ツールの互換性をチェックすると良いです。
もし既存ツールの利便性もよくない場合はオールインワンパッケージのIVRを利用するのもおすすめです。
セキュリティと信頼性
IVRは顧客との接点となる重要なインターフェースであり、個人情報や企業の重要情報を扱うことも少なくありません。
そのため、通信の暗号化、管理画面のアクセス制御、障害時のバックアップ体制など、セキュリティ面と運用の信頼性は導入判断における重要な基準です。
信頼できるベンダーの製品を選ぶことは、企業の信頼を守ることにもつながります。
まとめ
IVR(電話自動応答システム)は、電話取次業務の自動化による業務効率化やコスト削減、顧客満足度向上といった多くのメリットを提供する優れたツールです。
もしIVR導入を検討している場合は、自社の業務内容や顧客ニーズに合ったシステムを選ぶことが成功のカギとなります。この機会にぜひ導入をご検討ください。
たとえば、CallKeeperDXは、幅広い業種や規模に対応するIVRソリューションです。
通常はそれぞれ別に用意する必要がある、自動応答システムと通話録音システムが一体化しています。
また、現在使用している機器など環境そのままで利用可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
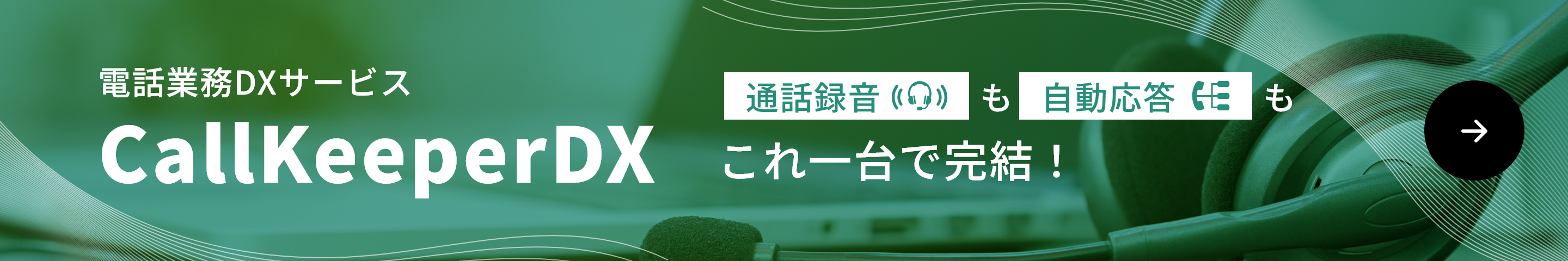
著者情報

辻 周平
扶桑電通株式会社 ビジネス推進本部
企画部 パッケージ推進課 チーフ
1982年生まれ 香川県出身。2010年扶桑電通株式会社入社。同社関西支店にて運送、製造業界を担当する営業としてお客様の業務課題の解決に向けたICTの導入を数多く経験。
その後2020年に現在のマーケティング職に異動し、お客様の電話を使った業務やカスタマーサポートのプロセスの最適化や効率化、利便性向上等電話業務全般に関わるコンサルティングに従事。日々お客様の電話業務にまつわる課題解決に取組んでいる。